
監修 大森武
専門学校で二輪整備の基礎から応用までを学び、卒業後は某国産バイクメーカーにて整備士としてキャリアをスタート。その後はバイク査定士としても活躍し、日々多種多様な車種と向き合っています。
現在の愛車は、ハーレーダビッドソンXL1200CX ロードスター。
“とにかくバイクが好き”という想いを原点に、初心者からベテランライダーまで幅広い層に向けて、信頼できる情報提供をモットーとしています。
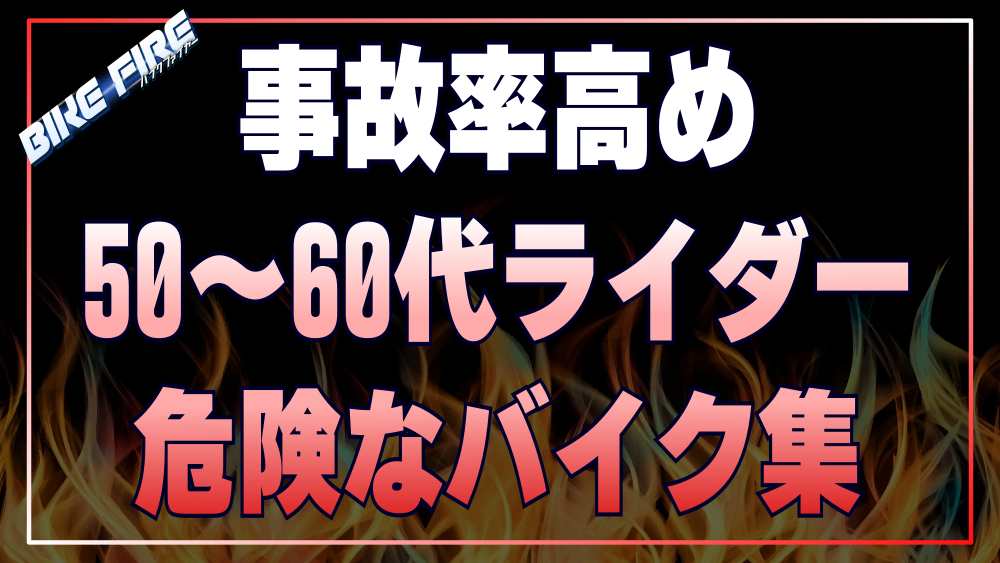

監修 大森武
専門学校で二輪整備の基礎から応用までを学び、卒業後は某国産バイクメーカーにて整備士としてキャリアをスタート。その後はバイク査定士としても活躍し、日々多種多様な車種と向き合っています。
現在の愛車は、ハーレーダビッドソンXL1200CX ロードスター。
“とにかくバイクが好き”という想いを原点に、初心者からベテランライダーまで幅広い層に向けて、信頼できる情報提供をモットーとしています。
バイクは年齢を問わず楽しめる趣味ですが、50代・60代のライダーにとっては注意が必要なモデルも存在します。特に、ある特定のバイクは死亡事故の割合が高く、高齢ライダーにとって危険度が増す傾向にあります。
なぜこれらのバイクが危険なのか? その理由は、強烈な加速性能、重すぎる車体、極端な乗車姿勢、そして制御が難しい特性にあります。若い頃には問題なく乗れていたバイクでも、加齢による体力や判断力の低下が影響し、思わぬ事故につながるケースが多発しているのです。

今回は「50代・60代は絶対に乗るな!」と警鐘を鳴らしたい、死亡事故が多すぎるバイク10選を紹介します。
あなたや大切な人が、無用なリスクを避けるための参考にしてください。


50代以上のライダーが気軽に乗ると、思わぬ事故や死亡リスクを引き起こすバイクとしてよく名前が挙がるのが「ホンダNSR250R」。その背景には、このマシンが誇る「レーシングスピリット」が深く関係しています。
ホンダNSR250Rは、1980年代から1990年代にかけて登場した伝説的なレーサーレプリカ。MotoGPのワークスマシン「NSR250」を模して作られたこのバイクは、まさにサーキットで戦うための性能を宿した一台です。特にトリコロールカラーのモデルは当時から現在まで不動の人気を誇ります。
1988年にリリースされた「MC18型」は、そのアイコン的な存在として知られています。このモデルのスペックを改めて見てみましょう
驚くべきは、この軽量な車体に45PSのパワーを搭載したことで、特に峠道で圧倒的な速さを見せつけた点です。
NSR250Rの最大の特徴は、パワーバンドが極端に効きすぎており、初心者や一般的なライダーには扱いが難しいこと。この特性により、特定の回転域で急激にパワーが噴き出し、制御不能に陥ることがあります。
また、コーナリング時にはアクセルを開け続ける必要があり、これを怠るとアンダーステアが生じて曲がりきれないという体験談が多数寄せられています。さらに、軽量車体に高性能ブレーキを組み合わせた設計により、強い制動をかけるとタイヤロックを起こし、転倒リスクが高まるという声も。
こうした「気難しい性格」を持つバイクゆえに、乗りこなすには高度な技術と集中力が求められるのです。
これほど事故が多発しているにもかかわらず、ホンダNSR250Rには根強いファンが存在します。「ドッカン加速」と称される一瞬のパワー爆発や、レーシングマシンそのものの感覚を味わえる点が、一部のライダーにとって何物にも代えがたい魅力なのでしょう。
実際、事故による破損やケガから立ち直り、多額の費用をかけて修理し再びNSR250Rに跨るライダーは少なくありません。その熱狂的な人気こそ、このモデルがいまだ多くの人を魅了し続ける理由です。


50代以上のライダーにとって、乗りこなすのが難しいバイクとして頻繁に挙げられるのが「カワサキ500SSマッハ3」。その異名である「走る棺桶」や「未亡人製造バイク」からも、このマシンの危険性が垣間見えます。
カワサキ500SSマッハ3は、1969年に登場した500ccクラスの2ストローク3気筒エンジンを搭載したモデルで、そのスペックは今なお語り継がれるほどです
注目すべきは、軽量な車体に高出力エンジンを搭載したことで、パワーウェイトレシオが2.9kg/PSと非常に高い点です。NSR250R(3.2kg/PS)と比較しても、圧倒的なパワーを誇っていました。
特にアメリカ市場をターゲットに開発されたこのバイクは、0-400m加速(通称ゼロヨン)で12秒を叩き出す驚異的な速さを実現しました。この性能は、500ccエンジンの枠を超えたもので、当時は他に並ぶものがなかったとされています。
その驚異的なエンジン性能とは裏腹に、500SSマッハ3は当時の技術制限も相まってバランスに難がありました。例えば、以下のような点が多くの事故を誘発する要因となりました
これに加えて、エンジン性能に他のパーツが追いついておらず、操作性の欠如が顕著でした。
その設計上の不備にもかかわらず、アメリカではこのバイクが「クレイジーでクール」と評価され、大ヒットを記録。これが川崎ブランドの評判を確立する大きな契機となりました。一方、日本国内でも「男心をくすぐるバイク」として多くのファンを魅了し続けています。
現在でも、中古市場で状態の良いものは600万円以上という高値で取引されることもあります。高級車が買える価格帯にもかかわらず、それだけの価値を見出すライダーが後を絶たないのです。


「カワサキ ゼファー400」といえば、走り屋に愛されるネイキッドバイクとして知られています。しかし、その人気ゆえに初老ライダーにとってもリスクが伴うモデルとしてしばしば挙げられます。では、この名車の特徴や事故率が高まる要因について詳しく見てみましょう。
ゼファー400は、1989年に登場しました。当時、レーサーレプリカ全盛期でフルカウルモデルが主流だった中、クラシックなネイキッドスタイルを採用し、一世を風靡しました。そのルーツは1979年発売の「Z400FX」に遡るとされ、伝統ある4気筒エンジンがその特徴です。
主なスペックは以下の通りです
エンジン性能は高回転域でのトルクが強く、軽量な車体と相まってスポーティな走行が可能です。そのため、走り屋の間で高い支持を集めています。
ゼファー400の事故率が高い理由には、次の要因が挙げられます
また、アニメ「東京リベンジャーズ」では、主要キャラクター・ドラケンの愛車として登場し、その「男らしさ」を象徴する存在として描かれています。この影響で若い世代にも再び注目されている点も、事故率の上昇に寄与している可能性があります。
ゼファー400は、クラシックな外観や豊富なカスタムオプション、スポーティな走行性能など、多くの魅力を持っています。その一方で、扱いを誤ると命に関わるリスクが高まることも事実です。特に古いモデルの場合、購入前に十分な点検を行い、整備された状態で乗ることが重要です。


ヤマハ XJR400/Rは、ネイキッドバイクの象徴として高い人気を誇ります。特に若年層や集団走行を好むライダーたちに支持されており、その影響もあって事故率が高いモデルとして知られています。
XJR400/Rは、スポーツネイキッドというカテゴリーに属し、ストリートでの走行性能とデザイン性を兼ね備えた一台です。1993年に登場したこのバイクは、当時の馬力規制である53PSを限界まで活用した高性能が特徴です。
主要スペックは以下の通り
ゼファー400と比較すると若干軽量で、エンジンパワーが高いことが特徴。パワーバンドに入った際の瞬間的な加速力は、バイク好きの心を掴んで離しません。
XJR400/Rの事故率が高い背景には、以下の要因が挙げられます
XJR400/Rは、単なるバイクを超えて「愛される存在」として多くのライダーに支持されています。その証拠に、ネットには改造事例やレビュー、動画が数多く見られ、未だに中古市場での流通も盛んです。中古車価格が50万円台からと比較的手に入れやすいことも、初心者ライダーを惹きつけるポイントの一つです。
しかし、こうした手軽さと人気の高さが事故の増加にも影響している点は否めません。性能や扱いの難しさを理解し、自分の運転スキルに合ったバイクライフを心がけることが重要です。


ホンダ CBX400Fは1980年代のバイク史を語る上で外せない名車です。その高性能と美しいデザインが多くのライダーを魅了しましたが、同時に暴走族の愛用車としても知られ、事故率が高いバイクの一つに挙げられる理由となっています。
1981年に登場したCBX400Fは、ホンダが川崎Z400FXやヤマハXJ400といったライバルモデルに対抗する形で開発された4気筒ネイキッドバイクです。当時の技術を結集させたこのモデルの主なスペックは以下の通りです
特筆すべきは、量産市販車として世界初となる「インボードベンチレーテッドディスクブレーキ」や「ブレーキトルクセンサー型アンチダイブ機構」を搭載していた点です。この革新性が当時のライダーたちを熱狂させました。
また、ボディのコンパクトさやトリコロールカラーのデザインも大きな特徴です。エキゾーストパイプが「X」形状に見えるように配置されており、モデル名の「X」を表すとしてホンダ自身も広告で「Xの挑戦」としてPRしていました。
CBX400Fが事故率の高いモデルとされる理由は、その高性能とカスタム自由度にあります
CBX400Fは、単なるバイクを超えて1980年代の日本のモーターカルチャーを象徴する存在でもあります。アニメ「東京リベンジャーズ」にも、キャラクター「林田春樹(通称:パーチン)」の愛車として登場し、その時代背景と共にファンの心をつかんでいます。
CBX400Fは、その革新的な技術と美しいデザインで名車として語り継がれる一方、無謀な運転や不適切な改造が事故を招くリスクを抱えています。手に入れたなら、その価値を尊重し、安全運転を心がけることが大切です。


ホンダ CBR400Fは、1980年代を代表する名車の一つであり、CBX400Fの後継モデルとして登場しました。その高性能と革新的な技術により、多くのライダーを魅了しましたが、同時に事故率が高いバイクとしても知られています。
CBR400Fは、1983年に登場しました。CBX400Fの製造終了と同時期にリリースされ、性能面で大幅な進化を遂げています。その主なスペックは以下の通りです
CBX400Fの48PSから58PSへと大幅に馬力が向上しており、これは新技術「REV(回転数応答型バルブ休止機構)」の採用によるものです。この技術は、後にホンダの「VTEC」技術へと発展し、現在では車両にも広く採用されています。
REVは、中低回転域では2バルブのみを稼働させ、高回転域では4バルブ全てを稼働させる仕組みで、トルクと出力の両立を実現しました。この技術により、CBR400Fは高回転域でのパフォーマンスが飛躍的に向上し、独特のエンジン音がライダーたちを魅了しました。
CBR400Fが事故率の高いモデルとされる理由には、以下の要因があります
CBR400Fは、単なるバイクを超えて1980年代の日本のモーターカルチャーを象徴する存在です。アニメ「東京リベンジャーズ」では、キャラクター「黒川イザナ」の愛車として登場し、その独特な存在感を放っています。
CBR400Fは、その革新的な技術と高性能で多くのライダーを魅了しましたが、扱いを誤ると命に関わるリスクを伴います。特に中古市場では200万円を超える価格で取引されることもあり、その価値を尊重し、安全運転を心がけることが重要です。


ホンダ CB400T ホークIIは、1970年代を代表するネイキッドバイクであり、その愛称「バブ」でも広く知られています。そのエンジン音が「バーブー」と聞こえることからこの名がつけられ、暴走族の間でも人気を博してきました。しかし、古いモデルゆえの性能面での課題や改造の多さが事故率を高める要因となっています。
CB400T ホークIIは、1977年に登場した400ccクラスの2気筒バイクで、4気筒が主流になる前の市場を象徴する存在です。その主要スペックは以下の通り
2気筒エンジンを搭載し、乗りやすさに定評のあるバイクで、初心者にも扱いやすい設計となっています。また、トリコロールカラーやコンパクトなボディデザインが多くのライダーに愛されました。
CB400T ホークIIが事故率の高いモデルとして認識される背景には、以下の要因があります
CB400Tは単なるバイクを超えた文化的な象徴としても注目されています。アニメ「東京リベンジャーズ」では、250ccバージョンであるCB250Tが主要キャラクターたちの愛車として登場し、物語の中でも重要な役割を果たしています。この作品での登場が、CB400Tを含む「バブ」シリーズへの新たな注目を集めるきっかけとなりました。
CB400T ホークIIは、その乗りやすさと独特なデザインで今なお多くのライダーを魅了しています。しかし、古いバイクゆえの安全性能の限界や、無謀な運転が命のリスクを伴うことを理解する必要があります。歴史ある名車の価値を尊重し、安全運転を心がけることが大切です。


リターンライダーやシニア層に支持される一方、その高性能ゆえに事故率の高さが指摘されるスーパーバイクが「カワサキ Ninja H2/Carbon」です。一度は夢を諦めたスーパースポーツに手が届くようになったライダーたちがこのバイクを選ぶのも当然と言えますが、性能に振り回されるケースが少なくありません。
現在発売中の「Ninja H2 SX SE」を例に、その性能を見てみましょう
さらに、カワサキ独自の「ラムエア加圧システム」を搭載することで、出力は210PSにまで引き上げられます。この出力と重量を比較すると、パワーウェイトレシオは驚異の1.3kg/PS。この数字からも、加速性能が常識を超えていることが分かります。
Ninja H2は、以下のような性能の高さが事故を引き起こしやすい要因となっています
初代 Ninja H2のユーザーからも「頭のネジが外れている人が乗るバイク」とまで評されるほどの性能が、このモデルの事故リスクを物語っています。価格が300万円を超える高級バイクでもあるため、一度の事故がライダーにとっても経済的打撃となる点も忘れてはなりません。
Ninja H2はその性能を適切に活かすために、以下の安全策が推奨されています
性能を理解し、安全に楽しむことが、このバイクを最大限に活かすための鍵です。


スズキの誇るスポーツバイクの最高峰、それが「GSX-R1000R」です。その名を聞けば、多くのライダーが思わず心を躍らせるバイクですが、これまた高性能が故に操りきれず事故に繋がるケースも後を絶ちません。さらに、このモデルは2022年にユーロ5排ガス規制に対応できず生産終了し、現時点では後継車種が発表されていないことでも注目されています。
GSX-R1000Rは、スズキの技術力を結集したモンスターマシンです。そのスペックを見てみましょう
注目すべきは、驚異的なパワーウェイトレシオです。このバイクは1PSあたり1.03kgという軽さを誇り、ほぼ1:1の比率に近い性能を実現。アクセルをひねれば、爆発的な加速がライダーを新たな次元へと導きます。
その性能の高さから、GSX-R1000Rは操りきれないと命に関わるリスクを抱えています。以下が主なリスクポイントです
2022年に生産終了となったGSX-R1000Rですが、2025年にスズキから新たなスーパースポーツモデルが発表されるとの噂があります。このモデルがGSX-R1000Rの後継機として登場するのか、ライダーたちの期待が高まっています。
GSX-R1000Rのようなハイパフォーマンスバイクに乗る際は、以下の点に注意が必要です


カワサキ Ninja ZX-14Rは、長きにわたるフラグシップバイクとして君臨し、2006年から2020年に生産終了となるまでの14年間にわたり多くのライダーを魅了しました。その圧倒的なパフォーマンスと存在感が際立つ一方、高性能ゆえに操作ミスが事故につながるケースも指摘されています。
ZX-14Rは、スーパースポーツカテゴリーにおいて世界トップクラスの性能を誇り、ロングツーリングにも適した快適性を兼ね備えたバイクです。そのスペックは以下の通りです
1441ccの大排気量エンジンは、中低回転域からもトルクをしっかりと発揮し、街乗りから高速道路まで幅広いシチュエーションで快適な走行を提供します。さらに、ライディングポジションが比較的アップライトであり、長距離走行でも疲労が軽減される設計が特徴です。
このバイクが事故率を高める要因には、以下のポイントがあります
ZX-14Rはその圧倒的なエンジン性能とツーリング性能のバランスが魅力です。スーパースポーツバイクとしては快適性に優れ、初心者からベテランライダーまで幅広い層を引きつけます。
しかし、その高性能ゆえにライダー自身の技術や体力が要求されるバイクでもあります。適切なトレーニングや安全装備の使用、定期的な休憩を取りながらの走行が推奨されます。
バイクは年齢を重ねても楽しめる素晴らしい趣味ですが、選ぶ車種を誤ると、一瞬の判断ミスが命取りになることもあります。今回紹介したバイクは、特に50代・60代のライダーにとって危険性が高いモデルですが、それは決して「乗るな」という意味ではありません。むしろ、自分の体力や技術、そしてバイクの特性をしっかり理解し、安全に乗るための参考にしていただければと思います。
大切なのは、自分のライディングスタイルや身体の変化を正しく把握し、無理なく楽しめるバイクを選ぶこと。適切な装備を整え、安全運転を心がけることで、バイクライフをより充実したものにできるはずです。



年齢を理由にバイクを諦めるのではなく、今の自分に合ったスタイルで長く楽しんでいきましょう。安全第一で、これからも素晴らしいバイクライフを!
コメント