
監修 大森武
専門学校で二輪整備の基礎から応用までを学び、卒業後は某国産バイクメーカーにて整備士としてキャリアをスタート。その後はバイク査定士としても活躍し、日々多種多様な車種と向き合っています。
現在の愛車は、ハーレーダビッドソンXL1200CX ロードスター。
“とにかくバイクが好き”という想いを原点に、初心者からベテランライダーまで幅広い層に向けて、信頼できる情報提供をモットーとしています。
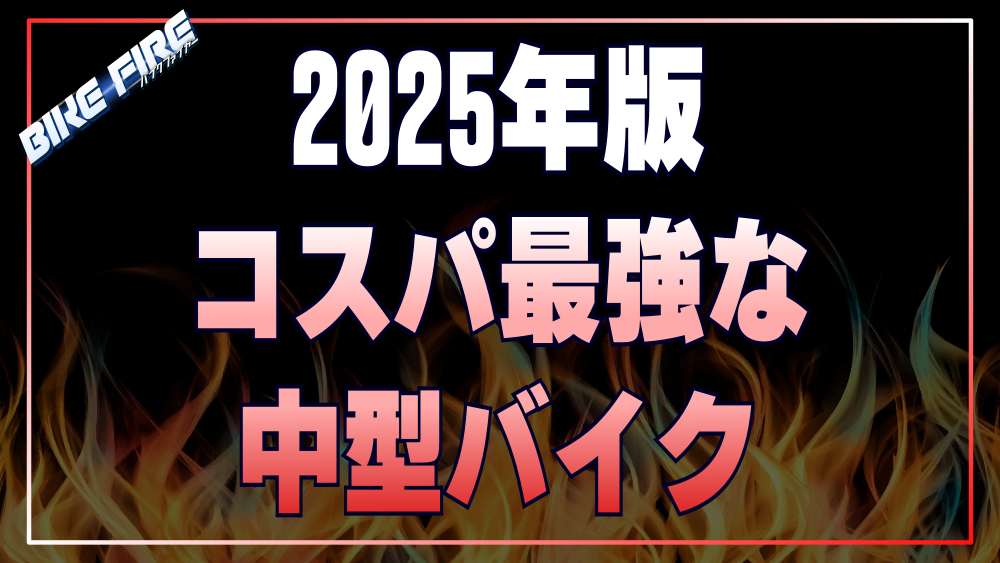

監修 大森武
専門学校で二輪整備の基礎から応用までを学び、卒業後は某国産バイクメーカーにて整備士としてキャリアをスタート。その後はバイク査定士としても活躍し、日々多種多様な車種と向き合っています。
現在の愛車は、ハーレーダビッドソンXL1200CX ロードスター。
“とにかくバイクが好き”という想いを原点に、初心者からベテランライダーまで幅広い層に向けて、信頼できる情報提供をモットーとしています。
2025年のバイク市場は、価格の高騰が続く中で、手頃な価格で高性能を誇るモデルが注目を集めています。特に250ccクラスのバイクは、新車価格が60万円を超えるモデルが増えている中、コストパフォーマンスに優れた選択肢が求められています。
これから紹介する各モデルは、コストを重視するライダーにとっての最適な選択肢として、2025年のバイクライフを豊かにしてくれることでしょう。

どのバイクがあなたのライディングスタイルにフィットするのか、一緒に見ていきましょう。





手頃な価格で手に入るフルカウルモデル
スズキのジクサーSF 250は、フルカウルのスポーツバイクながらも、本体価格約51万円という手頃な価格で購入できる数少ないモデルです。現在、新車の250ccフルカウルモデルは60万円以上が当たり前になりつつあり、50万円台で購入できるジクサーSF 250はまさに「最後の希望」と言える存在です。
ジクサーSF 250の心臓部には、スズキ独自の油冷単気筒エンジンが搭載されています。ホンダの水冷単気筒エンジンと比較しても燃費性能に優れ、日常の移動手段としても経済的に運用可能です。
エンジンスペック
このエンジンは燃費の良さだけでなく、トルクの厚みも確保されているため、市街地走行からツーリングまで幅広く活躍します。さらに、2025年はガソリン価格の高騰も懸念されており、燃費の良いモデルがより一層注目されるでしょう。
また、ジクサーSF 250は低価格ながらもラジアルタイヤや41mm正立フォークを装備しており、フルカウルスポーツらしい安定したコーナリング性能と制動力を確保。一般道だけでなく、高速道路での巡航性能にも優れています。
フルカウルモデルの大きな魅力は、走行時の防風性能です。特に冬場や高速走行時には、ネイキッドモデルに比べてライダーへの風圧が軽減されるため、長距離ツーリングでも快適に走行できます。
また、実用面でもジクサーSF 250は優れています。例えば、フェンダー(泥除け)を標準装備しており、雨の日の通勤や長距離移動でも泥はねを防げる仕様となっています。日常の足としても活躍できるのは大きなポイントです。
本体価格を抑えている分、デザイン面ではやや高級感に欠ける部分もあります。特に、ヤマハYZF-R25やホンダCBR250RRと並ぶと、デザインの質感に差を感じるかもしれません。しかし、10年前の250ccクラスのバイクと比較すれば、むしろ装備や性能は大幅に向上しており、価格以上の満足感を得られるでしょう。
「フルカウル=豪華なデザインが当たり前」というイメージがあるかもしれませんが、ジクサーSF 250は「シンプルかつ実用的なフルカウルモデル」として位置付けられます。もし、より高級感を求めるなら、大型バイクを検討するのも一つの手でしょう。





唯一無二の4気筒エンジンを搭載した250ccスポーツバイク
カワサキのZX-25Rは、250ccクラスでは希少な4気筒エンジンを搭載したスーパースポーツモデルです。2020年の発売以来、その高回転域での圧倒的なフィーリングと45〜48馬力のパワーで多くのライダーを魅了してきました。しかし、新車価格が96万円と高額なため、気軽に手を出しづらいバイクでもあります。
そんなZX-25Rですが、ついに中古市場で価格が下落し始めました。発売から5年が経過し、新車の流通量が落ち着いたことで中古市場でも在庫が増え、一部では手頃な価格で購入できるようになっています。ただし、2025年のバイク全体の値上げの影響もあり、すべての個体が安くなっているわけではないため、購入のタイミングを慎重に見極める必要があります。
ZX-25Rの最大の特徴は、250ccクラスでは唯一の直列4気筒エンジンを搭載していることです。
エンジンスペック(2023年モデル以降)
この高回転型エンジンにより、サーキット走行を想定した車体設計が施されており、250ccながらもまさに「スーパースポーツ」と呼べる走行性能を実現しています。ZXシリーズの思想を色濃く受け継ぎ、ライディングポジションや車体剛性も本格派。
「250ccの4気筒」というジャンル自体、過去を遡ると30年以上前のモデルにしか存在しませんでした。そのため、ZX-25Rは令和の時代に蘇ったロマンの塊とも言えるバイクです。
さらに、2023年モデル以降は48馬力へとパワーアップし、歴代最強のZX-25Rとなっています。
一方で、ZX-25Rはコスパを重視する人には少々厳しいポイントもあります。
ZX-25Rは発売から5年が経過し、今が中古市場での最安値に近い時期と考えられます。こうした高回転型4気筒エンジンを搭載した250ccクラスのバイクは、次の時代にはもう登場しない可能性が高いため、手に入れるなら今がラストチャンスかもしれません。
250ccクラス唯一の4気筒エンジンで圧倒的な高回転サウンドを楽しめる
サーキット走行を意識した本格的なスーパースポーツ設計
歴代最強の48馬力を誇る23年モデル以降は特に狙い目
中古市場で価格が下がりつつあるため、今が買い時の可能性あり
「250ccクラスで唯一無二の4気筒スポーツを所有したい」というライダーにとって、ZX-25Rはまさに2025年のコスパ最強な中型バイクの一台と言えるでしょう。





400ccなのに250ccより安い!?異例のコスパバイク
近年、バイクの価格は年々上昇しており、250ccクラスですら新車価格が60万円を超えるモデルが増えてきています。そんな中、Honda GB350は「400ccなのに250ccより安い」という異例の価格設定で、2025年現在もコスパ最強のバイクとして注目を集めています。
Honda GB350の新車価格は約56万円と、250ccクラスのバイクよりも安いという驚異的なコストパフォーマンスを誇ります。
例えば、同じHondaのCB250Rは2025年モデルが生産終了となったことで、250cc以上のネイキッドバイクは軒並み60万円以上に値上がり。しかし、GB350は大型バイク並みの排気量を持ちながら、250ccクラスよりも低価格を維持しているのです。
GB350の魅力は、その圧倒的なコストパフォーマンスにあります。
鬼燃費の空冷単気筒エンジン
GB350に搭載されているのは、空冷単気筒348ccエンジン。このタイプのエンジンは構造がシンプルで壊れにくく、さらに燃費性能も非常に優れています。燃費は40km/L前後と、250ccクラスのバイクに匹敵する低燃費を実現。
クラシックバイクならではの維持費の安さ
GB350は、スポーツモデルとは異なり、足回りのパーツが高額ではないのも魅力です。現代のスポーツバイクは高性能なラジアルタイヤや倒立フォークを搭載し、それに伴いメンテナンス費用も増加しています。しかし、GB350は昔ながらのシンプルな足回りを採用し、バイアスタイヤの選択肢もあるため、交換費用が抑えられます。
鼓動感を楽しめるエンジン特性
GB350は高回転域を回して楽しむタイプのバイクではなく、低速トルクを活かした鼓動感を楽しむのが魅力。最大トルクを3,000rpm付近で発生させるため、市街地でもストレスなく走れます。排気音もクラシックバイクらしく、乗るたびに「バイクに乗っている」という実感を味わえる仕様になっています。
シンプルな構造で故障しにくい
最近のバイクは電子制御が増え、メンテナンスが複雑になりがちですが、GB350は電子制御が最低限に抑えられているため、機械的な故障が少なく、長く乗れるのもメリットです。
コスパ最強のGB350ですが、400ccクラスゆえに車検が必要になる点は、250ccクラスと比較した場合のデメリットと言えるでしょう。
車検が必要(2年ごと)
250cc以下のバイクは車検が不要なため、維持費を安く抑えられます。一方で、400ccクラスのGB350は2年ごとに車検が必要。ただし、ユーザー車検を活用すれば1万円〜2万円程度で済ませることも可能です。
車検を受ける場所が限られる
ユーザー車検を受けるためには陸運局まで行く必要がありますが、都道府県によっては陸運局が1カ所しかない場合もあり、地域によっては不便に感じることも。
ほったらかしはNG!定期的な点検が必要
GB350は構造がシンプルな分、基本的なメンテナンスを怠ると、故障した際に余計な修理費がかかる可能性も。車検が面倒に感じる人や、頻繁な点検が苦手な人には向かないかもしれません。





クラシックスタイルの新星!待望の250ccクラスが登場
2024年末に登場したカワサキ W230は、クラシックバイクファン待望の新型モデルとして注目を集めています。250ccクラスのクラシックバイクは長らく新型が少なく、選択肢が限られていましたが、W230の登場により新たな選択肢が生まれました。
このモデルは、クラシックバイクの美しいデザインを持ちながら、コストパフォーマンスに優れた1台として評価されています。では、その魅力と弱点を詳しく見ていきましょう。
GB350と同じく、クラシック系ならではの維持費の安さ
クラシックバイクはスポーツバイクと違い、高性能なラジアルタイヤや倒立フォークを必要としません。W230もシンプルな足回りを採用しているため、メンテナンス費用を抑えることが可能です。バイアスタイヤの選択肢があるため、タイヤ交換のコストも比較的安価に済ませられます。
扱いやすいシート高と軽量な車体
W230のシート高はジャパニーズネイキッド世代のバイクとは異なり、スニーカーでも気軽に乗れる低めの設定。クラシックバイクならではのリラックスしたライディングポジションも相まって、長時間のツーリングでも疲れにくい設計となっています。
クラシックデザインと空冷エンジンの鼓動感
W230は往年のクラシックバイクを彷彿とさせるデザインを採用。タンク形状やシートデザイン、クロームメッキのパーツなど、見た目の美しさにもこだわった作りになっています。また、空冷単気筒エンジンならではの鼓動感も味わえるため、走行中の楽しさも十分に感じられるでしょう。
2025年時点では価格が安い部類
クラシックバイクは通常、作り込みが細かいため価格が高くなりがちですが、W230は250ccクラスのバイクとしては比較的安価な64万円前後。このクラスでこれ以上安い新車はほとんどなく、コストパフォーマンスは非常に高いと言えます。
250ccクラスとしては割高に感じる可能性も
W230はクラシックバイクとしての質感やデザイン性に優れていますが、230ccという排気量で64万円という価格設定に対しては賛否が分かれる可能性があります。GB350のように400ccで56万円という価格のバイクも存在するため、「排気量を重視するか、デザインや乗り味を重視するか」で評価が分かれるでしょう。
クラシックバイクならではの外装コスト
クラシックバイクは見た目の作り込みが重視されるため、転倒時の修理費用やカスタム費用が割高になりやすい傾向があります。特にW230は、メッキパーツやタンク形状にこだわりがあるため、傷がつくと修理費用がかさむ可能性があるのも注意点です。
スポーツ性能を求めると物足りないかも
W230はクラシックスタイルのため、スポーツバイクのような高回転域の伸びや俊敏なコーナリング性能は期待できません。あくまでクラシックバイクらしい、落ち着いた走りを楽しむためのモデルであることを理解しておく必要があります。





2気筒スポーツバイクのコストパフォーマンス最前線!
ヤマハのMT-25は、中型スポーツバイクの中でも特にコストパフォーマンスが優れた1台として注目されています。現在、250ccクラスの2気筒スポーツバイクは価格の上昇が顕著で、多くのモデルが70万円台へと突入している中、MT-25は63万円という圧倒的な低価格を維持しています。
しかし、2025年春にはヤマハの価格改定が発表されており、4月以降の値上げの可能性もあるため、コスパを重視するなら今が購入のタイミングと言えるでしょう。
本体価格63万円という驚異的な安さ
250ccクラスの2気筒スポーツバイクは、ここ数年で価格が大幅に上昇しており、現在では70万円を超えるモデルが一般的になっています。そんな中でMT-25は63万円という低価格を維持しており、予算を抑えてスポーツバイクを楽しみたいライダーにとっては非常に魅力的な選択肢となっています。
高回転型の2気筒エンジンで爽快な走り
MT-25は、最高出力35PSを発揮する並列2気筒エンジンを搭載しており、高回転までスムーズに吹け上がる特性が特徴です。街乗りでも扱いやすく、高速道路やワインディングでも十分なパワーを発揮するため、幅広いシチュエーションで楽しめるバイクとなっています。
ストリートファイタースタイルながら扱いやすいライディングポジション
MT-25は、シャープなデザインのストリートファイタースタイルを採用しつつも、ハンドル位置が適度に高めに設定されており、前傾姿勢がきつくなりすぎない設計になっています。そのため、ネイキッドバイクのような気軽さとスポーツバイクの楽しさを両立しており、初心者からベテランライダーまで幅広く支持されています。
MTシリーズの人気が再燃中
250ccクラスのスポーツバイク市場では、高価格化が進む中で「気軽に乗れるスポーツバイク」としてMTシリーズの人気が再び高まっています。事実、販売台数も好調であり、特に80万〜90万円の価格帯のバイクが手を出しにくいと感じるライダーにとって、MT-25は非常に魅力的な選択肢となっています。
サスペンションとタイヤの仕様はコスト重視
MT-25はコストパフォーマンスを重視しているため、足回りの装備は控えめな仕様となっています。リアタイヤは140mm幅のバイアスタイヤを採用しており、最近の250ccスポーツバイクで主流になりつつあるラジアルタイヤと比べると、グリップ性能や耐久性の面でやや劣る部分もあります。
アシスト&スリッパークラッチ非搭載
最近のスポーツバイクでは、シフトダウン時のリアタイヤのホッピングを抑えるアシスト&スリッパークラッチを搭載しているモデルが増えていますが、MT-25にはこの機能が採用されていません。ただし、すべてのライダーがこの機能を必要としているわけではなく、通常の街乗りやツーリングでは大きな問題にはならないでしょう。





最初のアドベンチャーバイクに最適な一台!
アドベンチャーバイクといえば、オフロード走行を意識した高い走破性や、ツーリングを快適にする充実した装備が特徴ですが、そのぶん価格が高くなりがちです。しかし、その常識を覆すのがスズキのVストローム250SXです。
250ccクラスのアドベンチャーバイクは軒並み高価格帯に突入する中、Vストローム250SXは50万円台という驚異的な価格設定を実現しており、初めてのアドベンチャーバイクとしても最適な選択肢となっています。
低価格で必要な装備がすべて揃っている
アドベンチャーバイクは、ツーリングを快適にするためにロングスクリーン、ハンドルガード、リアキャリアなどの装備が標準で搭載されることが多く、それが価格上昇の要因になっています。しかし、Vストローム250SXは約59万円という低価格で、こうした装備をすべて標準装備しています。追加パーツを買い揃える必要がなく、すぐにツーリングを楽しめるのが大きなメリットです。
油冷単気筒エンジンでパワーと燃費を両立
搭載される249ccの油冷単気筒エンジンは、軽量でありながらも力強いトルクを発揮し、市街地や峠道でも扱いやすい特性を持っています。さらに、燃費性能にも優れているため、長距離ツーリングでも給油の回数を抑えられるのが魅力です。
オフロード要素を取り入れた足回り
Vストローム250SXは、アドベンチャーバイクらしくオフロード要素を取り入れた足回りを採用しています。フロント19インチホイールを装備し、未舗装路でも安定した走行が可能です。林道ツーリングにも適しており、オンロードメインのモデルとは一線を画しています。
スズキらしいコスパの良さが光る1台
スズキのバイクは昔から「コストパフォーマンスに優れたモデルが多い」と評されてきましたが、Vストローム250SXはまさにその代表例です。近年のバイク市場は価格が高騰しており、250ccクラスでも60万円台後半~70万円台が一般的ですが、Vストローム250SXは50万円台で購入可能。これは、アドベンチャーバイクの中では非常に貴重な存在です。
高速道路の安定感は排気量なり
Vストローム250SXはパワフルな単気筒エンジンを搭載しているものの、高速道路の巡航性能はやや控えめです。特に2気筒エンジンを搭載する上位モデルのVストローム250と比べると、高速走行時の安定感は若干劣ります。しかし、一般道やワインディング、ちょっとした未舗装路を楽しむ用途では十分な性能を発揮します。
アドベンチャーバイクはサイズが大きめ
Vストローム250SXは軽量な部類のアドベンチャーバイクとはいえ、車体サイズは一般的な250ccバイクよりもやや大きめです。そのため、取り回しには慣れが必要で、特に足つきやUターン時の操作には注意が必要です。とはいえ、一般的なアドベンチャーバイクと比べれば十分扱いやすい設計となっています。





ミドルクラスのスポーツバイク市場において、カワサキ Ninja 400は長年にわたり圧倒的な人気を誇るモデル
2023年には同じカワサキからNinja ZX-4Rが登場し、さらにホンダも久々の4気筒250ccモデルを投入するなど、市場はますます激戦状態になっています。しかし、Ninja 400はそれらの影響をものともせず、依然として高い人気を維持しています。
なぜNinja 400は、どれだけ上位互換モデルが登場しても輝き続けるのか? その理由を詳しく解説していきます。
車体は250ccと共通、維持費も抑えられる
Ninja 400の最大の特徴のひとつは、基本的な車体設計がNinja 250と共通であることです。そのため、400ccクラスでありながらも、250cc並みの軽量な車体と扱いやすさを実現しています。
また、オイル量や消耗品のコストも250ccと同等で済むため、「維持費が思ったより安い」というのも魅力的なポイントです。400ccクラスのバイクは車検が必要になりますが、それを考慮してもコストパフォーマンスに優れた1台といえるでしょう。
400cc最強クラスの48馬力、160km/h台の実力
Ninja 400は、399cc並列2気筒エンジンを搭載し、最大出力48馬力を発揮します。車重が軽いことも相まって、400ccクラスとしてはトップクラスの加速性能を誇り、160km/h台のスピード域でも安定した走行が可能です。
かつて400ccクラスといえば、200km/h以上を狙える4気筒エンジンの時代もありましたが、現代の400ccスポーツバイクとしては十分すぎる性能を持っています。街乗りやワインディングはもちろん、高速道路での巡航性能も申し分ありません。
レギュラーガソリン仕様で経済的
400ccクラスのバイクの中には、ハイオク指定のモデルも多いですが、Ninja 400はレギュラーガソリンでOK。この点も、維持費を抑えたいライダーにとっては大きなメリットとなります。
車検の有無だけで選べる手軽さ
日本では250cc以下のバイクは車検が不要ですが、400cc以上は車検が必要になります。Ninja 400は、基本的にNinja 250と同じ車体を持っているため、「車検の有無で250ccか400ccかを選ぶ」というシンプルな選択が可能です。
「少しでも維持費を抑えたいならNinja 250、よりパワフルな走りを楽しみたいならNinja 400」という、明確な違いがあるため、どちらを選んでも後悔しにくいのが特徴です。
基本的にNinja 400に大きな弱点はありませんが、車体が250ccと共通なため、400ccクラスらしい重量感や迫力を求める人にはやや物足りないかもしれません。
また、Ninja 400に乗ると、「いずれ大型バイクに乗りたくなる」か、「250ccでもいいんじゃないか」と考えるライダーも多いです。これは、400ccとしては非常に扱いやすく、逆にいうと刺激が少ないともいえるためです。
とはいえ、Ninja 400はあくまで「実用的なミドルクラスのスポーツバイク」として設計されており、エントリーユーザーからベテランライダーまで幅広い層に受け入れられるモデルとなっています。





2025年、ホンダが新たに投入した「レブル250 Eクラッチ」
従来のレブル250にホンダ独自のセミオートマ技術「Eクラッチ」を搭載したモデルです。これにより、クラッチレバーを操作することなく、シフトアップ・シフトダウンが可能になりました。
この技術の登場により、特に都市部や渋滞の多いエリアでの快適性が大幅に向上し、初心者からベテランライダーまで幅広い層に支持されています。では、レブル250 Eクラッチが「最強バイク」といわれる理由を詳しく見ていきましょう。
セミオートマ技術「Eクラッチ」搭載で快適な走行
従来のクラッチ操作が不要になったことで、発進・停止がスムーズになり、渋滞や信号の多い都市部でもストレスなく運転できます。従来のクイックシフターと異なり、発進時からクラッチ操作を完全に省略できるため、スクーターのような手軽さと、マニュアルバイクの楽しさを両立している点が大きな魅力です。
アクセルを回すだけで力強い加速を実現
Eクラッチの恩恵により、レブル250の持つ力強いトルクをダイレクトに活かすことが可能になりました。通常のクラッチ操作では生じるわずかなロスがなくなり、アクセルを回すだけでスムーズかつ力強い加速を体感できます。結果として、従来モデルよりも出足の鋭さを感じられる仕様となっています。
長距離ツーリングでも快適な乗り心地
レブル250はもともと低重心で足つきが良く、長距離でも疲れにくいバイクとして評価が高いモデルでしたが、Eクラッチの導入により、さらに快適性が向上しました。クラッチ操作がないことで、長時間の走行でも手や指が疲れることがなく、ロングツーリングに最適なモデルといえます。
気軽に乗れる、私服でもOKなバイク
レブル250シリーズの人気の理由の一つが、「ライディングウェアにこだわらなくても乗れる気楽さ」です。フルカウルスポーツバイクのように「しっかりした装備を整えなければならない」という感覚がなく、普段着のままでも乗りやすいデザインが多くのライダーに支持されています。
特に、Eクラッチ搭載モデルでは「クラッチ操作がない=ストップ&ゴーが楽」という点が加わり、「軽快に街乗りを楽しみたい」というライダーにとって、より手軽なバイクになっています。
レブル250 Eクラッチの唯一の弱点は、価格が690,000円台と、従来のレブル250よりも高価である点です。「コスパ最強」と言われる250ccクラスの中では、決して安い部類ではありません。しかし、長く乗ることを前提とするならば、その価値は十分にあるといえます。
また、すでに半年以上の納車待ちになっているという情報もあり、今すぐ手に入れるのは難しい状況です。「どうしてもEクラッチ仕様が欲しい」という場合は、早めの予約が必要でしょう。
2025年の中型バイク市場は、コストパフォーマンスがますます重要視される中、魅力的なモデルが多く登場しています。今回紹介したバイクは、初心者からベテランライダーまで幅広い層に受け入れられる存在となっており、日常の足としてだけでなく、ツーリングや趣味としても楽しむことができます。
選択肢が豊富な今、どのモデルを選ぶかはライダー自身のライディングスタイルやニーズに大きく依存します。価格だけでなく、性能やデザイン、使い勝手など、様々な要素を考慮しながら、自分にぴったりの一台を見つけていただければと思います。



これからのバイクライフが、より充実したものになることを願っています。安全運転で、素晴らしい走行体験を楽しんでください。
コメント